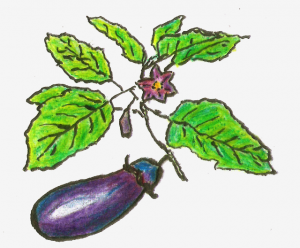 旧暦二月、八月は今の三月、九月で、季節は春と秋。春の彼岸は冬至から太陽が少しずつ勢いを増し、夜と昼の長さ、寒暖の差が変転し、草も木も生き物すべてが活動をはじめる節目の七日間で、三月二十日ごろを中心として中日、春分の日と言い、三日前の初日を彼岸の入り、三日後の最後は彼岸の明けと言われ、農作物が順調に育ち生物が繁茂して行くのを願います。秋の彼岸は夏至から猛威を奮った太陽が勢いを弱め、昼と夜の長さも変わり目で、九月二十三日ころが中日で秋分の日とされ、生き物達も成熟、収穫、休息期に向かいます。「暑さ寒さも彼岸まで」と言われます。時には「なに事ぞ彼岸過ぎてのこの暑さ(或いはこの寒さ)」もありますが。
旧暦二月、八月は今の三月、九月で、季節は春と秋。春の彼岸は冬至から太陽が少しずつ勢いを増し、夜と昼の長さ、寒暖の差が変転し、草も木も生き物すべてが活動をはじめる節目の七日間で、三月二十日ごろを中心として中日、春分の日と言い、三日前の初日を彼岸の入り、三日後の最後は彼岸の明けと言われ、農作物が順調に育ち生物が繁茂して行くのを願います。秋の彼岸は夏至から猛威を奮った太陽が勢いを弱め、昼と夜の長さも変わり目で、九月二十三日ころが中日で秋分の日とされ、生き物達も成熟、収穫、休息期に向かいます。「暑さ寒さも彼岸まで」と言われます。時には「なに事ぞ彼岸過ぎてのこの暑さ(或いはこの寒さ)」もありますが。
春分・秋分の日は、昼と夜の長さが全く同じで、その日太陽は真東から昇って真西に沈むというのです。『俳諧歳時記栞草』に「時正は彼岸の中日を云う。中日は、年中の昼夜少しも長短なく同じき故、時の正しきを以て云う也」とあります。太古より人びとは太陽と月や星の動きを注目し、観察し、関連づけ、何より大切な食=農への知識や知恵を得て来ました。春は作物を育てて農作業などの仕事に励み、秋は取り入れ収穫に万全を期するのです。
本来彼岸ひがんは仏教用語で、人が生死に苦しみ、迷い、悩む現実のこの世を此岸しがんとし、そこから超越し、自由、不動の仏のさとりの境地を彼岸、一には到彼岸(波羅蜜多はらみった)と言います。『続日本紀』淳仁天皇天平宝字二年(758)八月十八日の詔勅に、「摩訶般若波羅蜜多は、諸仏の母なり。四句の偈などを受持し読誦すれば、福寿を得ること思量すべからず。これをもって天子念ずれば、兵革・災難、国内に入らず、庶人念ずれば、疾疫・病気、家中に入らず。惑を断ち、祥を獲ること、これに過ぎたるはなし。宜しく天下諸国につげ、男女老少を論ずることなく、口にしずかに般若波羅蜜多を念誦すべし」とあります。弘法大師も、『摩訶般若波羅蜜多心経』(いわゆる般若心経)を、「謂うべし、簡にして要、約にして深し」と説きます。
上掲『続日本紀』淳仁天皇詔勅の「四句の偈」とは、諸行無常(ものみなすべて無常である)、是生滅法(これ生滅の法なり)、生滅滅已(生滅滅しおわりて)、寂滅為楽(寂滅を楽とす)で、『平家物語』冒頭の「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」は特に有名です。
『摩訶般若波羅蜜多心経』は別に「大いなる智慧の完成の眼目エッセンス」とも言われます。智慧の完成(到達)は生死にかかわるもろもろの苦悩や迷妄からの超越というのですが、個人のみでなく常に他者と生者、死者を問わず、さらには生きとし生けるもの達すべてへのまなざしがあることで、おかげさまでとなります。「般若心経」の
○羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶(ぎゃ-てい ぎゃ-てい はら-ぎゃ-てい はらそうぎゃ-てい ぼでいそわか)は「わかった 自分もわかった 他者もわかってくれた これで良いのでしょうか」となり、いったんは解決しても生き続ける限り変動して止みません。ノ-ベル文学賞にもなったリチャ-ド・バック『カモメのジョナサン』を思い起こします。
山頭火に「濁れる水の流れつつ澄む」があり、「独慎」と題する一文に、「一切は流転する。流転するから永遠である、ともいへる。流れるものは流れるがゆえに常に新しい。生々死々、去々来々、そのなかから、或はそのなかへ、仏が示現したまふのである」とあります。
○うつりきてお彼岸花の花ざかり
○こころすなほに御飯がふいた
○まことお彼岸入りの彼岸花
○お彼岸のお彼岸花をみほとけに
○あたたかい白い飯がある
○飲みたい水が音たててゐた
○折りて仏にたてまつるお花もひがん
○噛みしめる飯のうまさよ秋の風
○いただいて足りて一人の箸をおく
 お彼岸には春、秋ともにもち米で餅をつくりお供えします。もち米は直前によくとぎ、目盛一つ下の水加減で炊き、丸めて、小豆餡や大豆のきな粉、ゴマなどをまぶします。小豆餡は、一晩水につけ、多目の水で沸騰したら、いったんアク抜きで捨て、再度水を入れ換え、あとは気長にコトコト煮て、皮が破れたら何回かに分けて好みの砂糖を入れ、十分に煉り上げて仕上げます。餡を外にまぶすだけでなく、中に包めば、ごはんの上にトロロ昆布や青海苔の粉末、ゆかり(シソの粉末)などで飾っても美味しいです。春は牡丹の花にちなみ牡丹餅ぼたもち、秋は萩の花でおはぎです。
お彼岸には春、秋ともにもち米で餅をつくりお供えします。もち米は直前によくとぎ、目盛一つ下の水加減で炊き、丸めて、小豆餡や大豆のきな粉、ゴマなどをまぶします。小豆餡は、一晩水につけ、多目の水で沸騰したら、いったんアク抜きで捨て、再度水を入れ換え、あとは気長にコトコト煮て、皮が破れたら何回かに分けて好みの砂糖を入れ、十分に煉り上げて仕上げます。餡を外にまぶすだけでなく、中に包めば、ごはんの上にトロロ昆布や青海苔の粉末、ゆかり(シソの粉末)などで飾っても美味しいです。春は牡丹の花にちなみ牡丹餅ぼたもち、秋は萩の花でおはぎです。
また彼岸には桜めし(秋は紅葉モミジめし)の炊き込みごはんです。といだお米は水一目盛少なくして小一時間置き、火にかける間際に酒と醤油を好みでまわし入れます。炊き上ったら、さっくり混ぜ合わせると、醤油がほんのり心地良く香ります。
古来、日本人は神仏にお供えしたものを、下され物として、「おさがり」と言い、いただいて、共に食するよろこびとして来ました。
ありがたかね、こまんか魚たちの命ばもろうて、私たちは生かされとる
◇◇◇杉本 栄子氏 ◇◇◇石牟礼道子『苦海浄土』
